2025.07.07
【採用担当者必見】定着率を上げる方法8選|採用ミスマッチを防ぎ、離職率を下げる秘訣
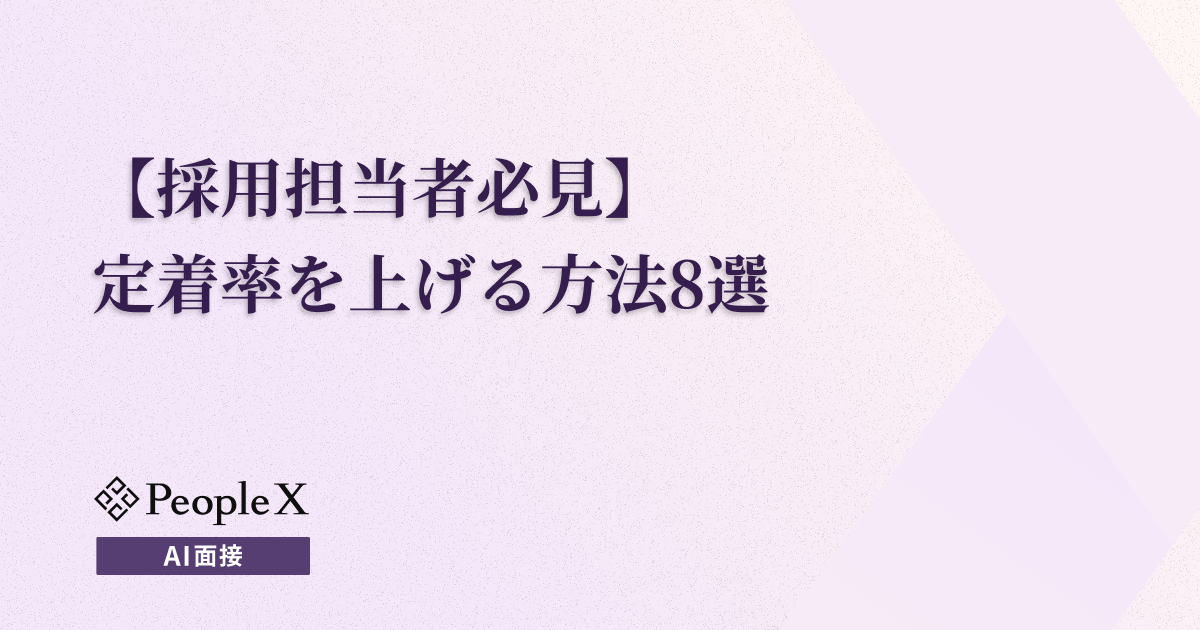
採用段階から始める定着率向上|ミスマッチを防ぎ、社員が辞めない組織を作る方法とは
「せっかく時間とコストをかけて採用したのに、すぐに辞めてしまった…」
「最近、若手社員の離職が続いている気がする」
採用担当者として、このような悩みを抱えていませんか。人材の流出は、採用コストの増大や現場の負担増につながるだけでなく、社内の士気低下も招きかねません。実は、この問題の根っこには「採用のミスマッチ」が隠れていることが多いのです。
この記事では、社員が辞めてしまう根本的な原因を解き明かし、採用段階から入社後まで一貫して取り組める「定着率を上げるための具体的な施策」を8つ紹介します。自社の状況を把握する方法から、明日から始められる実践ステップまで、わかりやすく解説します。この記事を読めば、採用ミスマッチを防ぎ、社員が長く活躍してくれる「辞めない組織」作りのヒントがきっと見つかるはずです。
まず知っておきたい「定着率」の基礎知識
定着率の改善に取り組む前に、まずは「定着率」という言葉の正しい意味と、自社の現状を客観的に知ることが大切です。ここでは、定着率の計算方法と、日本の平均的な離職率について解説します。現状を把握することが、効果的な対策への第一歩となります。
そもそも定着率とは?自社の現状を把握する計算方法
定着率とは、ある一定期間にどれだけの社員が会社に残り続けたかを示す指標です。この数値が高いほど、社員が会社に満足し、長く働き続けていることを意味します。計算方法はとてもシンプルです。
定着率(%) =
(期間終了時に在籍している社員数 ÷ 期間開始時に在籍していた社員数) × 100
例えば、4月1日に100名いた社員が、翌年の3月31日に90名になっていた場合、その年の定着率は90%となります。まずはこの計算式を使って、自社の定着率を算出してみましょう。
日本の平均離職率との比較|あなたの会社は大丈夫?
自社の定着率を把握したら、世間一般の数値と比べてみましょう。厚生労働省の調査によると、2022年の1年間の離職率は15.0%でした。これは、定着率に換算すると85.0%となります。
また、新卒社員の離職率は特に注目すべきポイントです。大学卒業後3年以内の離職率は32.3%にも上ります。つまり、新卒社員の約3人に1人が3年以内に会社を辞めている計算になります。あなたの会社の数値は、この平均と比べていかがでしょうか。もし平均よりも離職率が高い場合は、早急な対策が必要です。
なぜ優秀な人材は辞めてしまうのか?定着率が低い5つの根本原因
社員が会社を去る決断をする背景には、必ず何らかの理由が存在します。給与や待遇だけでなく、もっと根深い問題が隠れていることも少なくありません。ここでは、定着率が低くなる代表的な5つの原因を掘り下げていきます。自社に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
【原因1】採用のミスマッチ|入社後のギャップが早期離職を招く
早期離職の最も大きな原因が「採用のミスマッチ」です。「こんなはずじゃなかった」という入社後のギャップが、社員のモチベーションを大きく下げてしまいます。例えば、求人票や面接で聞いていた仕事内容と実際の業務が違ったり、社風が想像と異なっていたりするケースです。採用時に良い面ばかりを伝えすぎると、このギャップはより大きくなり、不信感へとつながります。
【原因2】労働環境への不満|長時間労働や不十分な休日
過度な長時間労働や休日出勤が当たり前になっている環境は、社員の心と体をむしばんでいきます。ワークライフバランスを重視する価値観が広まる中で、プライベートを犠牲にするような働き方は敬遠される傾向にあります。十分な休息が取れなければ、生産性も低下し、結果として優秀な人材ほど早く見切りをつけてしまうでしょう。
【原因3】人間関係の悪化|コミュニケーション不足とハラスメント
職場の人間関係は、仕事の満足度に直結する重要な要素です。上司や同僚に気軽に相談できない雰囲気や、部署間の連携が取れていない状況は、社員に大きなストレスを与えます。また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの問題が放置されている環境は論外です。安心して働けない職場に、人は定着しません。
【原因4】評価・給与制度への不信感|納得感のない処遇
自分の頑張りが正当に評価されず、給与や昇進に反映されないと感じると、社員は会社への貢献意欲を失います。評価基準が曖昧だったり、上司の好き嫌いで評価が決まったりするような状況では、不満が募るばかりです。「なぜあの人が評価されるのか」「自分の成果は認められていない」という不信感は、転職を考える大きなきっかけとなります。
【原因5】キャリアへの不安|成長機会や将来性の欠如
「この会社にいても、スキルアップできない」「自分の将来像が描けない」といったキャリアへの不安も、離職の引き金となります。特に向上心の高い優秀な人材ほど、自身の成長を強く望むものです。日々の業務が単調で学びの機会が少なかったり、会社として明確なキャリアパスを示せていなかったりすると、より成長できる環境を求めて外の世界へ目を向けるようになります。
【採用から見直す】定着率を向上させるための具体的な施策8選
定着率が低い原因がわかったら、次はいよいよ具体的な対策です。大切なのは、採用活動の時点から「定着」を意識すること。ここでは、採用フェーズと入社後フェーズに分けて、効果的な8つの施策を紹介します。できることから一つずつ取り組んでいきましょう。
【採用フェーズ】ミスマッチを防ぐための3つの施策
入社後のギャップをなくすことが、定着率向上の第一歩です。採用段階でいかに「お互いの理解」を深められるかが鍵となります。
1. 採用基準の明確化とペルソナ設計
まず、「どんな人に来てほしいのか」を具体的に定義しましょう。スキルや経験だけでなく、会社の文化や価値観に合う人物像(ペルソナ)を詳細に設計することが重要です。これにより、面接での質問内容が具体的になり、評価のブレも少なくなります。
2. リアルな情報提供による期待値調整
会社の良い面だけでなく、課題や厳しい面も正直に伝えましょう。「残業は月平均〇時間程度ある」「繁忙期はチームで協力して乗り越える文化がある」など、リアルな情報を提供することで、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージできます。これが「こんなはずじゃなかった」を防ぎます。
3. 体験入社やリファラル採用の導入
ミスマッチを防ぐ強力な方法として、体験入社や社員紹介(リファラル採用)があります。候補者に実際の職場を体験してもらうことで、仕事内容やチームの雰囲気を肌で感じてもらえます。また、社員からの紹介であれば、信頼できる情報をもとに応募してくれるため、カルチャーフィットしやすい傾向があります。
【入社後フェーズ】エンゲージメントを高める5つの施策
無事に入社してもらったら、次は社員が「この会社で働き続けたい」と思える環境を作ることが大切です。社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高める施策を見ていきましょう。
4. 働きやすい労働環境の整備
長時間労働の是正や有給休暇の取得促進はもちろん、テレワークやフレックスタイム制度の導入など、柔軟な働き方を検討しましょう。社員一人ひとりが自分に合った働き方を選べる環境は、ワークライフバランスの向上に直結し、満足度を高めます。
5. 公平で透明性のある人事評価制度の構築
誰が見ても納得できる、公平で透明性の高い評価制度を作りましょう。評価基準を全社員に公開し、定期的なフィードバック面談を行うことが重要です。「何を頑張れば評価されるのか」が明確になれば、社員は目標を持って業務に取り組むことができます。
6. キャリアパスの提示とスキルアップ支援
社員が社内での将来像を描けるよう、明確なキャリアパス(昇進や異動のモデルケース)を示しましょう。また、資格取得支援制度や研修プログラムを充実させ、社員の「成長したい」という意欲を後押しすることも大切です。会社が自分のキャリアを応援してくれていると感じられれば、エンゲージメントは自然と高まります。
7. 社内コミュニケーションの活性化
部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションを促進しましょう。定期的な1on1ミーティングや、社内イベント、メンター制度の導入などが効果的です。風通しの良い職場は、人間関係のストレスを減らし、チームワークの向上にもつながります。
8. オンボーディングと定期的なフォロー体制の強化
新入社員がスムーズに職場に慣れるための「オンボーディング」プログラムは非常に重要です。入社後数ヶ月間は、人事や配属先の上司が定期的に面談を行い、悩みや不安を早期にキャッチアップする体制を整えましょう。丁寧なフォローが、孤独感をなくし、早期離職を防ぎます。
明日から始める!定着率改善に向けた4つの実践ステップ
「やるべきことはわかったけど、何から手をつければいいの?」と感じるかもしれません。ここでは、定着率改善をスムーズに進めるための4つのステップを紹介します。この流れに沿って、着実に改善を進めていきましょう。
Step1:定着率の現状分析と課題の可視化
まずは、自社の定着率を計算し、部署別・年代別・入社年次別など、細かくデータを分析してみましょう。どの層で離職が多いのかを特定することで、問題の所在が明確になります。「若手社員の3年以内離職率が高い」「特定の部署だけ定着率が低い」など、具体的な課題を洗い出すことがスタートです。
Step2:従業員サーベイや面談による離職要因の特定
数字だけでは見えない「なぜ辞めるのか」という理由を探るため、従業員満足度調査(サーベイ)や、退職者へのヒアリング、既存社員との面談を実施しましょう。アンケートや面談を通じて、労働環境、人間関係、評価制度など、現場のリアルな声を集めることが、的確な対策を立てるための鍵となります。
Step3:優先順位をつけた改善策の計画と実行
集まった声をもとに、課題解決のための具体的な施策を計画します。すべての課題に一度に取り組むのは難しいため、「影響が大きく、すぐ着手できるもの」から優先順位をつけましょう。例えば、「コミュニケーション不足」が課題なら、まずは部署内の1on1ミーティングから始めるなど、スモールスタートを意識することが成功のコツです。
Step4:施策の効果測定と継続的な見直し
施策を実行したら、必ず効果測定を行いましょう。定着率の推移を定期的にチェックしたり、再度従業員サーベイを実施したりして、施策の効果を検証します。思うような結果が出なければ、その原因を探り、やり方を見直すことが重要です。定着率改善は、この「実行→測定→改善」のサイクルを回し続ける地道な活動なのです。
定着率向上に成功した企業の取り組み事例
理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことも大切です。ここでは、定着率の改善に成功した企業の取り組みを2つ紹介します。自社で応用できるヒントが隠されているかもしれません。
事例1:採用基準の見直しで早期離職率が劇的に改善したIT企業
あるIT企業では、新卒の3年以内離職率が40%を超えていることが長年の課題でした。原因を分析したところ、スキル重視の採用がカルチャーミスマッチを生んでいたことが判明。そこで、採用基準に「会社のビジョンへの共感」や「チームワークを大切にする姿勢」といった項目を追加しました。面接では、具体的なエピソードを深掘りする質問を徹底。結果として、3年以内離職率は15%まで劇的に改善しました。
事例2:コミュニケーション施策でエンゲージメントを高めた製造業
従業員数300名のある製造業では、部署間の連携不足と人間関係の希薄化が問題でした。そこで、社長自らが全社員と面談する「ラウンドテーブル」や、部署を横断したランチ会への費用補助、感謝を伝え合う「サンクスカード」制度などを導入。これらの施策により、社内の風通しが格段に良くなりました。従業員サーベイでもエンゲージメントスコアが大幅に向上し、離職率も業界平均を大きく下回る水準まで低下したのです。
まとめ:定着率は採用戦略と一体。継続的な改善で強い組織を目指そう
ここまで、定着率を上げるための具体的な方法について解説してきました。重要なポイントは、定着率の改善は「採用」と「入社後の育成・環境整備」の両輪で考える必要があるということです。
採用段階でミスマッチを防ぎ、入社後には社員が安心して長く働ける環境を整える。この一貫した取り組みが、社員のエンゲージメントを高め、結果として会社の成長を支える「強い組織」を作り上げます。
定着率向上は、一朝一夕に実現するものではありません。しかし、この記事で紹介したステップに沿って、自社の課題と向き合い、一つひとつ改善を積み重ねていけば、必ず成果は現れます。まずは自社の定着率を計算することから始めてみませんか。あなたの会社が、社員一人ひとりにとって「働き続けたい」と思える場所になることを心から応援しています。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。

