2025.07.17
構造化面接とは?メリットやデメリット、質問例をわかりやすく解説
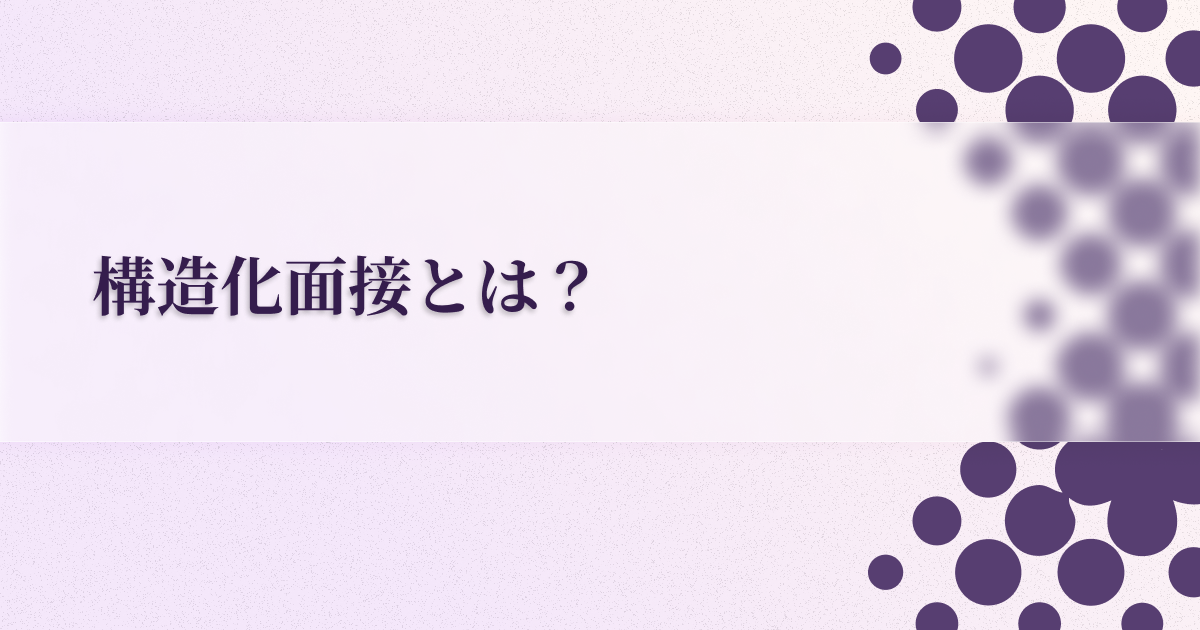
構造化面接は信頼性が高く、客観的に評価ができる手法として、広く利用されてきました。あらかじめ決められた質問を順番どおりに行うため、面接官の主観を限りなく排除できます。
本記事では、構造化面接の概要や、非構造化面接・半構造化面接との違い、メリット・デメリットについて詳しく解説します。また、AI面接についてもお伝えしますので、人材採用を見直したい方は参考にしてください。
構造化面接とは
構造化面接とは、人材採用における評価のばらつきを最小限に抑え、公平で信頼性の高い選考を実現するために設計された面接手法です。ここでは、構造化面接の特徴と「非構造化面接」や「半構造化面接」との違いについて詳しく解説します。
構造化面接の特徴
構造化面接とは、すべての応募者に対して同じ質問を同じ順序で行う面接手法です。構造化面接の特徴は、次の2つに集約されます。
- 事前に設定された質問項目と評価基準
- 手順通りの面接形式
構造化面接では、募集する人材やボジションに応じて、最適な質問と評価基準を事前に設定して面接を行います。質問に対する回答を評価する際には、設定された評価基準に基づいてスコアリングするのが一般的です。
この手法により、面接官ごとの価値観や印象によるバイアスを排除でき、客観的かつ定量的に応募者の能力を測ることができます。
面接形式も定まっているため、複数の面接官がいる場合でも、面接官の技量にかかわらず同じように面接を進められるのも特徴のひとつです。
「非構造化面接」や「半構造化面接」との違い
構造化面接以外にも、「非構造化面接」や「半構造化面接」といった手法があります。
非構造化面接とは、質問の内容や順番を事前に定めず、面接官がその場の流れや回答に応じて、自由に面接を進める手法です。対話型の面接手法で、応募者の自然体を引き出すことができる点では優れていますが、評価基準が曖昧になったり面接官の力量に評価が左右されたりといったリスクが生じます。
一方、半構造化面接は、構造化面接と非構造化面接の中間にあたる手法です。事前に設定された質問項目を軸にしつつも、必要に応じて面接官が自由に質問を加えて深堀りできるのがメリットです。非構造化面接ほど比較基準にばらつきはありませんが、質問の掘り下げ方や反応の捉え方にブレが生じるといった課題が残ります。
以下に、主な違いを表にまとめました。
| 構造化面接 | 半構造化面接 | 非構造化面接 | |
| 質問の内容 | 事前に決められた質問のみ | 一部は決められた質問。必要に応じて面接官が追加で質問 | 面接官が自由に設定 |
| 質問の順序 | 同じ順序 | 基本の順序はあるが、柔軟に変更可能 | 面接官が自由に設定 |
| 評価基準 | 同じ評価基準 | 一部は同じ評価基準。追加質問では面接官の主観に依存 | 面接官の主観に依存 |
構造化面接のメリット
構造化面接は、単なる質問のテンプレートではなく、採用プロセス全体の品質を高められる手法です。主なメリットについて詳しく見ていきます。
評価基準を公平にできる
構造化面接の大きなメリットは、評価基準を公平にできることです。質問と評価基準が統一されているため、すべての応募者を同じ視点で比較できます。
面接官の主観や先入観、あるいはその日の面接官のコンディションといった不確定要素を排除できるようになり、公平な評価が可能になります。特に、ダイバーシティ推進を目指す企業にとって、無意識のバイアスを排除できるという観点からも有効です。
採用業務の効率化が図れる
採用業務の効率化を図れることもメリットのひとつです。応募者全員に対して同一の質問で面接を進められるため、採用フローをよりシンプルに構築できます。
また、面接結果を数値化しやすい点も大きなメリットです。採用後は、応募者のスコアと実際の職場適応度を照らし合わせることで、翌年の質問設計や評価項目の見直しに活かせます。
ほかにも、構造化面接であれば、オンライン環境でも一貫性のある評価が可能です。
採用後のミスマッチが起こりにくい
構造化面接では、求める人物像や必要なスキルを事前に採用基準として設定できるため、採用後のミスマッチが起こりにくいのもメリットです。そのため、採用後に「想定していた人物像と一致しない」「期待していた能力が発揮されない」といったギャップを減らせます。
構造化面接のデメリット
構造化面接には利点だけでなく、いくつかの課題も存在します。導入を検討する際は、こうした懸念点についてもあらかじめ把握しておくことが重要です。
機械的・事務的な質問になりやすい
構造化面接では、あらかじめ面接の内容が決まっており、機械的・事務的な質問になりやすい点がデメリットです。応募者によっては「尋問されているようだ」「冷たい面接官だ」と感じることもあります。
また、面接の雰囲気が堅くなりがちなため、応募者も発言しにくくなり、本来の人間的な魅力を探るのが難しくなります。このようなデメリットを避けるためには、面接官が柔らかい口調を心がけるなど、雰囲気づくりの工夫が必要です。
質問作成や変更の作業に手間がかかる
構造化面接は、役職やポジションごとに適した質問を作成したり変更したりしなければならず、想像以上に作業に手間がかかります。また、業務内容に変更が生じた場合は、それに応じて質問や評価項目の見直しが必要です。小規模企業にとっては、設計段階のハードルが高いと感じられるかもしれません。
潜在的な能力を見極めるのが難しい
構造化面接では、設定された行動や状況に対する回答を基に評価を行うため、枠に収まらない創造性や将来的な成長ポテンシャルといった、まだ現れていない能力を測るのは難しいのが実情です。
このようなデメリットを補うためには、ほかの面接手法との併用がおすすめです。
構造化面接の質問例
構造化面接では、応募者の具体的な行動や意思決定の背景を把握するために、「行動面接」や「状況面接」といったタイプの質問が用いられます。ここでは、それぞれの質問内容をいくつかお伝えしましょう。
行動面接の質問例
行動面接では、過去の経験に基づいた質問を投げかけ、応募者の行動特性や価値観を引き出します。通常、以下のような質問が用いられます。
- これまでにチームで大きな課題を乗り越えた経験を教えてください。そのときのあなたの役割と行動を具体的に教えてください。
- 目標を達成するために、あなたはどのように行動しましたか。また行動した結果、最終的に得られた成果を教えてください。
- これらの経験から、次にどのような目標を立てますか。
状況面接の質問例
状況面接では、仮定の状況を提示し、応募者がどう行動するのかを問います。これは、思考の柔軟性や問題解決能力を測るうえで役に立ちます。
- 納期が差し迫っているなか、チームメンバーが急遽休むことになりました。あなたなら、どのように対処しますか。
- 顧客から理不尽なクレームを受けたとき、どのような対応を取りますか。
- 複数のプロジェクトを同時に進めなければならないとき、優先順位をどう判断しますか。
構造化面接を実現するAI面接とは
近年では、構造化面接の効率をさらに高める手法として「AI面接」の導入が進んでいます。AIが面接官となれば、人間の感情や主観を排除でき、より公平な面接が可能となるでしょう。
ここでは、AI面接の特徴やメリット、デメリットを解説します。AI面接について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
AI面接とは?メリットや導入時の注意点・ポイントを詳しく解説
AI面接の特徴
AI面接とは、応募者がAIによる自動質問システムと対話し、その内容を記録・分析して評価する面接手法です。応募者は、パソコンやスマートフォンから、好きな時間に面接を受けられるという利点があります。また企業側も、面接官の業務を調整する必要がなくなります。
AI面接では、質問に対する回答内容だけでなく、声のトーンや話す速度、言葉の選び方、表情などの非言語情報も記録され、アルゴリズムによりスコア化されるのが特徴です。統一された基準で数値化でき、比較が可能となるため、構造化面接の「公平性・再現性」という利点をさらに強化できます。
AI面接の流れ仕組み
AI面接はサービスやプラン内容によって異なりますが、通常、次のような流れで面接を行います。
- 応募者への案内と準備
- オンライン面接
- AIによる分析と評価
- 結果の作成
- 選考
まずは、応募者に、面接のための専用の面接URLやアプリを案内します。応募者は、パソコンやスマートフォンから、通知のあったURLなどにアクセスし面接を受けます。面接では、あらかじめ用意された質問が画面に表示され、応募者はカメラに向かって回答していく形が一般的です。
面接後は、AIが応募者の回答内容やスキル、経験のレベル、理論性、コミュニケーション能力など幅広い角度から評価します。さらに、AIによって評価はレポートの形に生成されるため、採用担当者は必要な情報をわかりやすい形で入手できます。
採用担当者は、レポートをもとに次の過程に進む応募者を選定し、最終的な合否の判断を行うのが通常の流れです。
AI面接のメリット・デメリット
AIを活用した面接手法が多くの企業で取り入れられつつある背景として、企業と応募者の両方にとって、利便性が高いという理由があります。一方で、AIならではの制約や、従来の対面面接とは異なる注意点もあります。
導入前にAI面接のメリット・デメリットを把握しておきましょう。
メリット
AI面接の主なメリットは、次のとおりです。
- 公平で客観的に評価できる
- 採用業務を効率化できる
- 時間や場所にとらわれない
人間の主観が入りやすい面接において、AI面接であれば、同一の基準で評価を行える点がメリットです。「なんとなくいい印象」といった曖昧な感覚ではなく、音声や表情などから数値的なデータを基に分析ができるため、公平で客観的な評価が実現します。
また、大量の応募者がある場合でも、並行して面接を進められ、企業側の工数削減につながります。応募者側は、自分の都合にあわせて好きな時間・好きな場所で面接を受けることが可能です。遠方に住む応募者も気軽に面接を受けることができ、幅広い層にアプローチできます。
デメリット
AI面接のデメリットには、次のようなものが挙げられます。
- 導入に費用と専門知識が必要である
- 評価基準が不透明な場合がある
- 多様性を評価しづらい
- AI面接に苦手意識を持つ応募者がいる
AI面接のデメリットは、導入に費用と専門知識が必要な点です。中小企業の場合、リソースが限られるため、導入が難しい場合もあるでしょう。
AI面接のデメリットのひとつは、また、評価基準が不透明な点もAI面接のデメリットです。多くのAI面接では、どのようなアルゴリズムやデータに基づいて評価しているのか不透明です。
そのため、意図せず偏りのある評価が導き出されているケースがあるかもしれません。たとえば、女性のデータよりも男性のデータのほうが多い場合、女性に不利な評価が出るおそれもあります。
また、AI面接では、人間の多様性を評価しづらい点もデメリットとして挙げられます。AI面接を利用する場合は、事前に設定した基準にあてはまらない応募者がいる点も理解しておく必要があるでしょう。かなければなりません。
AI面接に慣れた応募者がいる一方で、苦手意識を持つ応募者も少なくありません。人間相手ではないAIという面接官に対して、どのように振る舞えばいいのかわからず、十分にアピールできないと感じる応募者もいます。AI面接を用いることで、能力や才能のある人材が、正当に評価されずに選考から漏れてしまう可能性がある点には注意が必要です。
まとめ
構造化面接は、採用における評価のばらつきを最小限に抑えられる面接手法です。非構造化面接や半構造化面接と比べて、評価の一貫性や再現性に優れています。ただし、面接が形式的になりやすいことや、導入や運用に手間がかかるといった課題もあります。
昨今、構造化面接の運用をさらに効率化できる方法として注目を集めているのが、AI面接です。AI面接は、採用業務を効率化できたり幅広い層にアプローチできたりとメリットが大きい反面、評価基準の不透明さ透明性や多様性の評価人間的な対応の難しさといった課題も残るため、導入する際には慎重な検討が必要です。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。

